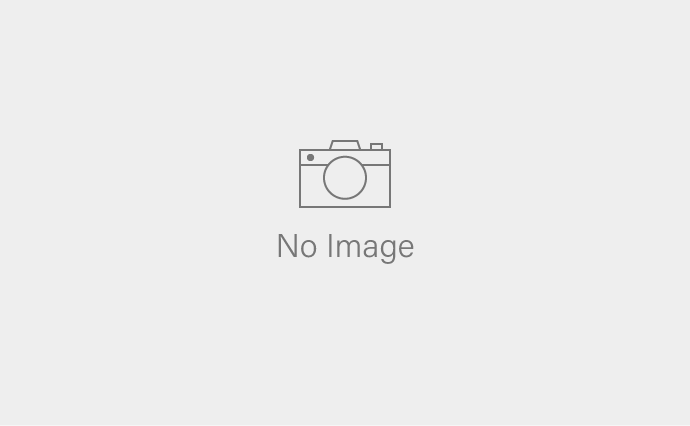■見出しまとめ ・ゼロトラストセキュリティの基本を知る
・ゼロトラストセキュリティが必要な理由
・ゼロトラストセキュリティ導入の具体例
・ゼロトラストセキュリティ導入でよくある疑問
・ゼロトラストセキュリティ成功のカギ
・ゼロトラストセキュリティの事例と効果
―――――――――――――――――――――――――――
世界的にサイバー攻撃の被害額は年々増え続けており、IDCの調査によると、2025年にはセキュリティ関連の支出が2兆円を超える見通しです。企業や組織を取り巻く脅威が高度化するなか、注目を集めているのが「ゼロトラストセキュリティ」。外部はもちろん、内部からの不正侵入をも想定した堅牢な仕組みが求められる時代に、本記事ではその基本と具体的対策をわかりやすく解説いたします。セキュリティ対策をより強固にしたい方に向け、導入のヒントや成功事例を丁寧にご紹介しますので、ぜひご参照ください。
―――――――――――――――――――――――――――
【ゼロトラストセキュリティの基本を知る】
ゼロトラストセキュリティとは、あらゆるアクセスを「信頼しない」という前提で安全対策を行う考え方です。名前にある「ゼロトラスト」は「誰も信用しない」という意味合いを強調しており、組織の内外を問わず、すべての通信やアクセスを疑いながら検証する仕組みを構築します。
たとえば、社内ネットワークに接続している社員であっても、アクセス権限が適切かどうかを常に検証します。これは「一度システムに入ってしまえば全てにアクセスできる」という従来の仕組みと大きく異なります。こうすることで、内部からの情報漏えいや意図しない不正使用を防ぐのが大きなねらいです。
ゼロトラストセキュリティを理解するうえで重要なのは、次のポイントです。
- 常時認証と監視:ネットワーク内外のアクセス状況を継続的にチェックする
- 最小権限の徹底:業務に必要な最低限のアクセス権だけを付与する
- 継続的な検証:利用状況や脅威の変化に応じて設定を見直す
これらを徹底することで、外部はもちろん、内部からの攻撃リスクも下げられます。さらに、機密情報にアクセスできる人物やデバイスを正確に把握できるので、後から監査しやすいというメリットも得られます。
―――――――――――――――――――――――――――
【ゼロトラストセキュリティが必要な理由】
従来のセキュリティ対策は「外部からの侵入を防ぐ」ことが中心で、ファイアウォールや仮想専用線による境界防御が主流でした。しかし現代では、業務のデジタル化が進み、クラウドサービスやテレワーク利用によって「境界」が曖昧になっています。社員や取引先が、どこからでも業務にアクセスできるようになる一方、攻撃者の手口も巧妙化し、内部システムへの侵入経路が増えてしまいました。
たとえば、
- ウイルスメールの巧妙化により、気づかないうちに端末が乗っ取られる
- 正規の権限を持ったユーザーが悪意を持ち、情報を持ち出す
- テレワーク端末の通信を狙い、不正なアクセスを試みる
こうした状況下で組織を守るには、従来の「外を防げばOK」という発想では限界があります。そこで注目されるのがゼロトラストセキュリティです。何度も本人確認を行い、実際に利用できる範囲を最小限に保つことで、情報漏えいを防げる可能性が高まります。
さらに、IPA(情報処理推進機構)のデータでも、内部犯行や誤操作が原因の情報漏えいが全体の3割以上にのぼるという結果が示されています。こうした事態を未然に防ぐためにも、ゼロトラストの考え方は大きな効果を発揮します。
―――――――――――――――――――――――――――
【ゼロトラストセキュリティ導入の具体例】
ゼロトラストセキュリティを導入する際には、以下のプロセスを踏むことが一般的です。大がかりなイメージを抱く方もいらっしゃるかもしれませんが、組織の規模や利用環境に応じて段階的に進めることが可能です。
- 現状把握
- 保有しているシステムやデータの棚卸し
- 既存のアクセス権限や認証方式の確認
- 内部ネットワークの構成を再点検
- アクセスコントロールの導入
- 多要素認証の採用(パスワードとワンタイムコードの併用など)
- 利用者ごとに最小限の権限のみ付与
- デバイスのセキュリティ状態を常に監視
- ネットワークの分割
- 機密性の高いセグメントを区切って重要データを保護
- 部署・業務別でセキュリティルールを設定
- 万が一侵入されても被害を抑える仕組みづくり
- 可視化と監査
- ログを定期的に確認し、不審な動きを早期に把握
- 監査レポートを作成し、改善点を洗い出す
- 定期的にルールを見直し、常に最新の対策を適用
これらを踏まえて進めると、ネットワークのどの部分に脆弱性があるのかが分かりやすくなります。また、必要に応じて段階的に強化できるため、中小規模の組織でも取り入れやすいといわれています。最初から完璧に導入できなくても、段階的なアプローチで少しずつ強固な環境をつくることが大切です。
―――――――――――――――――――――――――――
【ゼロトラストセキュリティ導入でよくある疑問】
ゼロトラストセキュリティを検討される方からは、よく下記のようなご質問をいただきます。疑問を解消しておくことが、スムーズな導入の第一歩です。
Q1.「導入コストが高そうですが、小さな会社でも実現できますか?」
- A:段階的に導入することで、大規模投資を一度に行わずに済みます。まずは重要なシステムだけゼロトラスト化し、その後順次拡大する方法を選ぶ企業も少なくありません。
Q2.「認証やチェックが増えると、社員の負担が大きくならないでしょうか?」
- A:多要素認証などは一見手間が増えるように感じますが、慣れれば大きな負担ではないと報告する企業が多いです。また、シングルサインオンなどの仕組みをうまく組み合わせることで、利便性と安全性を両立しやすくなります。
Q3.「クラウドサービスとの相性はどうでしょう?」
- A:むしろクラウドとゼロトラストセキュリティは相性が良いとされています。業務がさまざまなクラウド環境に散らばるほど、アクセス権を細かく制御する必要があるため、ゼロトラストの概念が活きる場面が増えます。
このように、導入に際しての不安点は多種多様ですが、どんな組織でも共通して言えるのは「最初に全てを完璧にする必要はない」ということです。順序立てて着実に取り組むことで、安全性と利便性のバランスを保ちながら移行することができます。
―――――――――――――――――――――――――――
【ゼロトラストセキュリティ成功のカギ】
ゼロトラストセキュリティを成功に導くには、技術面だけでなく運用面も含めた総合的な対策が欠かせません。特に注意したいのは、次の点です。
- 経営者・管理層の理解
- セキュリティ強化には投資や組織体制の変更が必要
- 経営側が方針を明確にし、社員を巻き込むことでスムーズに導入できる
- 現場とのコミュニケーション
- 運用に影響が出る変更をする場合、現場の声を取り入れる
- 新しい認証方式やネットワーク分割に関しては事前研修を行う
- 継続的な教育とルールづくり
- フィッシングメールの手口や新たな脅威に常に備える
- セキュリティポリシーを更新し、定期的に周知徹底する
- 定期的な検証と改善
- セキュリティ脆弱性がないか診断を受ける
- 過去のインシデントを振り返り、新たな対策を検討
これらの取り組みを行うことで、ゼロトラストセキュリティが「形だけの導入」にならず、実際に機能する仕組みになります。とりわけ組織全体でセキュリティ意識を共有し、全員が少しずつ責任感を持つことが、トラブル回避への近道と言えるでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――
【ゼロトラストセキュリティの事例と効果】
近年、大手企業から中小企業まで、ゼロトラストセキュリティを取り入れつつある組織が増えています。たとえば、国際的に事業を展開する企業では、各国の拠点からクラウド上のデータにアクセスするケースが日常的に発生します。このとき、拠点ごとに厳格な認証とアクセス権限を設定しておけば、万が一どこかの端末が侵害されても他拠点への被害が広がりにくくなります。
実際、海外拠点でセキュリティ事故が発生したものの、ゼロトラストの仕組みによって被害を最小限にとどめた事例も報告されています。さらに、大規模なクラウドサービスを利用する組織ほど、ゼロトラストの効果を実感しやすい傾向があるようです。
- 多要素認証導入後、フィッシング被害が激減
- 最小権限の原則を徹底した結果、内部犯行リスクが減少
- 社内外への遠隔接続端末が増えても、統一された認証方式で管理可能
これらの成果により、情報漏えいを防ぐだけでなく、社内のセキュリティ意識を高める副次的な効果も生まれています。安心して業務が行える環境を整えることで、生産性の向上にもつながると期待されています。
―――――――――――――――――――――――――――
【まとめ(約200文字)】
ゼロトラストセキュリティは、外部だけでなく内部の脅威も想定しながら、すべてのアクセスを逐一検証する仕組みです。多要素認証や最小権限の原則を徹底することで、攻撃者の侵入を防ぎ、万が一侵入されても被害を最小限に抑えられます。導入時の不安やコストは段階的な取り組みで緩和可能です。経営者から現場まで一体となった運用こそが、ゼロトラストの真価を発揮するカギになります。
―――――――――――――――――――――――――――
【クロージング(約300文字)】
「守りは最大の攻撃なり」という言葉が示すように、今の時代、セキュリティを強固にすることが組織の成長と信頼を支える大切な要素となっています。ゼロトラストセキュリティの導入によって、リスクを軽減しながら新しい働き方やビジネスチャンスに挑む姿勢を後押しできます。ぜひ、今回ご紹介した基本概念や手順を参考に、まずはできる範囲で導入を検討してみてはいかがでしょうか。何かご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後に、みなさまの組織では「いまのセキュリティで本当に守りきれるのだろうか?」と、改めて問いかけたいと思います。この問いに向き合うことで、組織の未来を守る対策が一歩進むかもしれません。ゼロトラストの重要性を心に留めつつ、今一度セキュリティの在り方を考えてみてください。